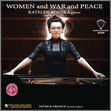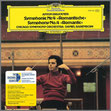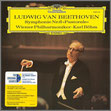Classical Records
主な入荷済みレコード 一覧(2024年7月23日現在)
・価格・在庫状況は各レコードのジャケットをクリックしてください。
入荷しましたレコードは、入荷当日からご購入いただいた順に発送しております。
お手元に届くまで今暫くお待ち下さい。
新譜と主な予約可能レコード
7月以降の入荷予定です。
高音質 Chasing the Dragonのクラシック ダイレクト・カッティング盤

レコード録音の究極の形と言われる《ダイレクト・カッティング》盤、それはジンプル・イズ・ベストをそのまま行うことで、デジタルなどへの変換を行わず、マイクからの信号を直接レコード盤面に刻み込みます。
しかし、演奏者への負担は大きく、ミスがあっても編集作業による修正は出来ないので、やり直しとなります。
当然制作費は通常のレコードより高くなり販売価格にも反映されてしまいますが、この音の魅力を知ってしまうと抜け出せません。
当然ですが、再生する装置、特にプレーヤー回りには細心の注意が必要となります。
上記4タイトルは、新たにダイレクト・カッティングにより生まれた最新のアナログ・レコードですが、なかなか入手しない希少盤です。ただ、今ならお取り寄せ出来ます。
シギスヴァルト・クイケンの生誕80年を記念して名盤が発売中です。
2024年はシギスヴァルト・クイケン生誕80年にあたり、これを記念してACCENTレーベルの名盤5タイトルがLP化されます。ラッカー盤の行程をなくし直接マザー盤にダイレクトに溝を刻む「DMMカッティング」(Direct Metal Mastering)を採用しており、良好な音質が期待できます。 また、レコード各面の収録時間を20分程にして余裕のあるカッティングにより振幅を大きく取り音質的にも有利にしています。
詳細はジャケットをクリックしてご覧下さい。
ASTRÉEの高音質盤名盤が復刻されました。
故・長岡鉄男氏が「厚みとアブラっこさ、艶はナンバーワン、時にはしつこいくらい」と名調子で表現したASTRÉEの高音質名盤、《マラン・マレ:ヴィオール曲集第2巻より》《F.クープラン:ヴィオール作品集》の2タイトルがALIA VOXより復刻されました。
演奏は、古楽界の巨匠中の巨匠のジョルディ・サヴァール(vg)を中心に同世代の名手と共にフランスのサン・ランベール・デ・ボワ教会にて行われた演奏を収録しています。
教会での収録と言うこともあると思いますが、残響音までが濃厚な空気感を持っていて、他では聴くとの出来ない柔らかで豊かな音質には心が洗われます。
録音は、ドクター・トーマス・ガリアが担当し、マスタリングにはマヌエル・モヒノがあたっています。
完全生産枚数限定盤 Serial No. 付き
発売中。 33rpm 180g Stereo LP 各¥4,600 (税込・送料別)
TELARCの名録音盤が久々の登場です。

1977年にサウンド・エンジニアのジャック・レナーと音楽プロデューサーのロバート・ウッズにより設立されたTELARCは、アメリカのマーキュリー・レコードが実践した全指向性マイクロフォンを左右+中央に配置するマイクセッティングを基本として、明瞭な定位を確保し、リミッターやイコライザーに頼らないデッカ・レコードやRCAレコードとも異なる音作りを行いました。
当初はダイレクトカッティングのみ行っていましたが、1978年からはデジタル録音を行い高音質のD/Aコンバーターにより変換して
レコード化を行っていました。
本物の大砲を録音し、今までに無い程のダイナミックレンジの広さで一斉を風靡したエリック・カンゼル指揮/シンシナティ交響楽団によるチャイコフスキー:序曲1812年が大ヒットしたことによりTELARC = 高音質盤メーカーとして世界中で認知されるようになりました。
しかし、同じ時期に録音・発売されながら影に隠れてしまったレコードがこの「展覧会の絵」です。
録音される1ヶ月前の1978年9月の来日公演時には「展覧会の絵」も演奏され、クリーヴランドの弦の音色ってこんなに美しかった?、金管は流石アメリカのオーケストラだ!など様々な完動を与えました。
1812年の音質はデモには最適ですが、演奏はマゼール指揮/クリーヴランド管弦楽団が圧勝です。
勿論録音もRCA Living Stereoの高音質盤フリッツ・ライナー指揮/シカゴ交響楽団を凌ぐ程です。
私の記憶では、レコードで復刻されたことは無かったように思います。
合唱録音の最高峰 4タイトルが揃いました。
合唱の高音質盤と言えば、proprius 『カンターテドミノ』が上げられますが、最近では、Chesky Record* の優秀録音を更に高音質化したAudioNautes Recordingsの『大いなる神秘』が人気です。
また、『イースターのための合唱曲集』は、Positive Feedback 2020 Writer's Choice Award Winner ! を授賞しました。
『ラウダーテ Ⅱ』は、AudioNautes Recordingsの傑作盤であることは間違いないのですが、こちらは殆ど入荷しないためこれ程の名演・名録音を知る人が少なく残念です。
合唱録音の最高峰と言われる4タイトルが一緒に揃うことはあまりありません。
Berliner Philharmoniker が自ら手掛けた戦時のフルトヴェングラー最高音質のLP

先に発売された「フルトヴェングラー 帝国放送局(RRG)アーカイヴ 1939-45 SACD Hybrid盤から
厳選された音源を選んだ8LP BOXが全世界2,000セットのみSerial No.入りで販売されます。
Berliner Philharmoniker が自ら手掛けた戦時のフルトヴェングラー最高音質のLP登場です。

ダイレクト・カッティングによるラトルのブラームス交響曲全集やベートーベン交響曲全集、ハイティンクのブルックナー交響曲第7番などレコードの製作にも力を惜しまないBerliner Philharmonikerならではのものです。
ドイツ帝国放送局のオリジナルテープを初めて利用してハイレゾサンプリング、更に最新のデジタル技術により邪魔になる雑音のみを除去した結果、過去の全てのレコードに勝る決定盤になったことは、多くの録音賞授賞が物語りました。
また、見事な複刻は戦時下の激動の時代ならではの極限的でエキセントリック、そしてモダンで独特な演奏を一段と魅力的にしています。
チェリビダッケの最高傑作にしてブルックナー交響曲第8番の頂点
チェリビダッケの最高傑作どころか、ブルックナー演奏の頂点とまで賞賛された伝説のライヴ「チェリビダッケ、リスボン・ライヴ」がレコードの正規盤として発売されます。
この演奏はプライヴェート盤で発売されるや否やセンセーションを巻き起こしたうえに入手困難となり、ネットオークションでも高値を記録した幻の演奏です。
その演奏を完璧に再現できるよう正規オリジナルマスターにLP用のマスタリングを施し、慎重にカッティングを行い、切りあがったラッカー盤をキング関口台スタジオで入念に検聴、万全を期してレコード化されています。また、各楽章1面ずつの2枚組となっています。
極限をも超えた超スローテンポで全曲を貫徹。そして点描のようにあらゆるエレメントを彫琢してまいります。これはチェリビダッケ晩年の特徴的なアプローチでありますが、ここまでチェリビダッケの魔術が決まりに決まっている演奏は他にありません。演奏時間は100分を超え崇高な神々しさにはひれ伏すばかり。ミュンヘン・フィルの音色はどこまでも柔らかく繊細、ポルトガル大使館の協力で発見され、ご子息セルジュ・イオアン・チェリビダキ氏とミュンヘン・フィルの承認を得て世に出た、 貴重極まる歴史的音源です。
古くて素敵なクラシック・レコードたち
2021年6月に文芸春秋社から発売された村上 春樹さんの『古くて素敵なクラシック・レコードたち』は、60年近くレコードを買い集めた中からジャズでは無くクラシックの『好きなレコード、面白いレコード』を486枚、100タイトルを紹介されています。
『クラシック音楽を愛好する方なら、ページを繰るってジャケット写真を目にしているだけで、ある程度親密な気持ちになっていただけるのではないかと推測する(希望する)。』と書かれていますが、私もすっかり親密な気持ちになり、レコードファンであれば誰もが思うことも沢山書かれていて何度も頷いてしまいました。
紹介されている素敵なレコードの多くはCD化されていますが、やはりレコードで聞いてみたくなります。
Shop.では、100タイトルの中から現在も購入出来るレコードを紹介しますので本をクリックしてご覧下さい。